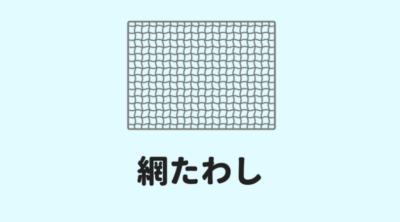「本を読むのが遅い」と感じることはありませんか?読みたい本はたくさんあるのに、1冊を読み終えるのに何日もかかってしまう。そして気づけば本棚には積読(つんどく)の山ができている…。これは多くの読書好きが抱える共通の悩みです。
読書が遅い原因は大きく分けて2つあります:
- 時間の確保が難しい:忙しい日常の中で読書時間を作れない
- 読書スピードそのものが遅い:1ページを読むのに時間がかかる
私自身、この両方の問題を抱えていました。特にビジネス書や新刊は鮮度が重要なので、できるだけ早く読み終えたいと思いつつも、なかなか読み進められないジレンマに悩んできました。
2025年現在、情報過多の時代だからこそ、効率的な読書法を身につけることは大きなメリットになります。書籍から得られる深い知識や洞察は、オンラインの断片的な情報では得られないものです。
この記事では、読書スピードを上げる実践的な方法と積読を解消するテクニックを、それぞれのタイプ別に詳しく解説します。「時間が取れない人」と「読むスピードが遅い人」、どちらのタイプにも効果的な対策を紹介するので、あなたの読書生活が劇的に変わるはずです。
では、あなたの「本を読むのが遅い」悩みを解決する方法を見ていきましょう。
読書スピードが遅い原因と7つの効果的な改善策
本を読むのが遅いと感じる悩みは多くの人が抱えているものです。読みたい本はたくさんあるのに、思うように読み進められないとストレスを感じますよね。
読書が遅い原因は大きく分けて2つのタイプがあります:
読書の2つの壁:
- 時間確保の問題:読書する時間そのものが取れない
- 読書速度の問題:読む速度自体が遅く、1冊に時間がかかりすぎる
これらの問題は別々に対策を考える必要があります。特にビジネス書などは情報の鮮度が重要なので、効率よく読み進める技術が欠かせません。
あなたの読書スピードは平均より遅い?簡易チェック方法
自分の読書スピードが本当に遅いのか確認してみましょう。平均的な読書速度は以下の通りです:
一般的な読書スピードの目安:
- 遅い読者:1分間に100〜200語
- 平均的な読者:1分間に200〜250語
- 速い読者:1分間に400語以上
- 訓練された速読者:1分間に1,000語以上
簡単にチェックする方法としては、標準的な文庫本1ページ(約400字程度)を読むのにかかる時間を測定してみましょう。1ページ1分以上かかっている場合は、改善の余地があるかもしれません。
スマートフォンなら「読書速度計測アプリ」も便利です。短い文章を読んで、WPM(Words Per Minute)を自動計算してくれます。
なぜ読書スピードを上げることが重要なのか
読書スピードを上げることには、単に多くの本を読めるようになる以外にも重要なメリットがあります:
読書スピード向上のメリット:
- 情報収集の効率化:ビジネスパーソンにとって、最新情報をいち早く取り入れる武器になる
- 集中力の向上:速く読むためには集中力が必要で、この力は他の活動にも良い影響を与える
- 脳の活性化:多くの情報を素早く処理することで、脳の認知機能が活性化される
- 時間の有効活用:空き時間を使って効率よく読書できるようになる
- 積読解消:読みたい本の山を効率よく減らせる喜びを感じられる
特に2025年現在では、情報過多の時代となり、効率的な情報処理能力がこれまで以上に重要になっています。読書スピードを上げることは、単なる趣味の域を超えた実用的なスキルといえるでしょう。
以降のセクションでは、それぞれの問題に対する具体的な改善策を見ていきます。まずは「読書時間を確保できない人」向けの対策から始めましょう。
読書時間を確保できず本を読むのが遅くなる人向け対策
「読みたい本はたくさんあるのに、なかなか読む時間が取れない…」
このような悩みを抱える人は非常に多いものです。日々の忙しさの中で読書の時間を確保することは、想像以上に難しいものです。しかし、工夫次第で読書時間を生み出し、積読を減らすことは十分に可能です。
効果的な読書時間の確保法:時間をしばる習慣づくり
読書になかなか取りかかれない最大の理由は、**「必要な時間が見込めないこと」**です。本を読み終えるのにどれくらいの時間がかかるか分からないため、ついつい「時間に余裕がある時に読もう」と後回しにしてしまいます。
皮肉なことに、時間に余裕ができたとしても、その余裕があるがゆえに「あと30分したらやろう」「食事の後でやろう」と先延ばしにしてしまう傾向があります。そして気づけば、また時間に余裕がなくなってしまいます。
この悪循環を断ち切るための有効な方法は、時間を決めて読書をすることです。具体的には:
読書の取り組み方:
- 読み終わるまで読むのではなく、時間で区切る
- 「読み始めて30分経ったら辞める」と決める
- 集中力が続く範囲の時間(15〜45分程度)に設定する
この方法を実践すれば、「この短い時間で何ページ読めるか」というゲーム感覚で取り組めるようになり、次第に読書の習慣が身につきます。2025年の研究でも、時間制限を設けることで行動へのハードルが下がることが確認されています。
読み始めるまでの手間を極力少なくする環境整備術
なかなか読書に取りかかれない別の要因として、**読書を始めるまでの「手間」**があります。この心理的ハードルを下げることで、読書習慣を格段に向上させることができます。
読書環境の整備は、単に本だけを考えるのではなく、読書という行為全体へのハードルを下げることが重要です。例えば:
読書環境を整える工夫:
- 本を手の届く場所に置き、すぐに読める状態にしておく
- 読書をする場所までの動線をスムーズにする
- 読書に関連する小道具(コーヒーなど)もすぐに用意できるようにする
デジタル読書をする場合は、スマートフォンのホーム画面でKindleなどの読書アプリを最も触りやすい位置に配置するという工夫も効果的です。SNSアプリを脇に移動させ、代わりに読書アプリを最前面に持ってくることで、無意識的にSNSをチェックする習慣から脱却できます。
このような小さな工夫の積み重ねが、長期的には大きな読書量の違いを生み出します。
読書の邪魔になるものを特定し排除する方法
読書に集中できない大きな原因は、周囲の誘惑や気を散らすものの存在です。電車の通勤中などに読書が捗るのは、他にやることがなく集中できるからです。
読書は目と脳を使う活動なので、他の活動と同時進行することは本質的に難しいものです。そのため、読書時間を確保するためには、読書の邪魔になるものを意識的に排除する必要があります。
集中力を高める環境づくり:
- テレビやSNSなど、気が散る誘惑を物理的に遠ざける
- 通知をオフにしたり、「おやすみモード」を活用したりする
- 読書に適した静かな環境を意識的に作り出す
特におすすめなのが**「お風呂読書」**です。お風呂は他の誘惑が極めて少ない空間であり、リラックス効果もあるため読書に最適な環境と言えます。防水ケースを使えば電子書籍リーダーも安心して使用できます。
また、「読書専用の時間帯や場所」を設定することも効果的です。例えば「毎朝の通勤電車では必ず読書をする」「寝る前の15分は必ず読書する」といったルールを作ることで、読書の習慣化が進みます。
諦めず読書量を増やす:オーディオブックの活用法
どうしても読書の時間が取れない場合、オーディオブックという選択肢も検討する価値があります。従来の読書は「読書のための時間」を確保する必要がありますが、オーディオブックなら他の活動と並行して「読書」できます。
オーディオブックの最大の魅力は、以下のような「ながら読書」が可能になる点です:
オーディオブックで可能になること:
- 家事や料理をしながらの読書
- 通勤・運転中の読書
- 運動しながらの読書
- 寝る前の暗い部屋での読書
2025年現在、Amazon Audibleやaudiobook.jpなどのサービスでは、プロのナレーターによる高品質な朗読を楽しめるタイトルが大幅に増加し、特にビジネス書や自己啓発書のラインナップが充実しています。多くのサービスで無料体験も提供されているため、試してみる価値は十分にあります。
また、最新の機能として、読書スピードの調整(1.5倍速、2倍速など)やスリープタイマーなども充実しており、より効率的に本を「聴く」ことができるようになっています。
視覚情報が必要な図や表が多い専門書には不向きな場合もありますが、物語性のある小説やエッセイ、ビジネス書などは十分にオーディオブックで楽しめます。「読むための時間がない」という理由で読書を諦める前に、ぜひ検討してみてください。
本を読む速度・理解するペースが遅い人向け対策
本を読むことはできるけれど、1冊を読み終えるのに何時間も、時には数日かけてしまうという方も多いのではないでしょうか。特にビジネス書は次々と新刊が出るため、読書に時間がかかりすぎると最新の知識を取り入れられなくなります。また、読書に時間を取られすぎて仕事や他の活動の時間が減ってしまうのは本末転倒です。
ここでは、読書スピードを上げながら内容理解も両立させるための実践的な方法をご紹介します。
読書速度を劇的に上げる:頭の中で音読(黙読)しない練習法
**「早く読むなら音読するな」というのは、速読の基本中の基本です。多くの人は無意識のうちに、文字を見ながら頭の中で音に変換してから理解しています。これがサブボーカリゼーション(黙読)**と呼ばれる現象で、読書スピードを大きく低下させる主な原因です。
人間の発声速度は1分間に約150〜200語程度ですが、視覚による情報処理速度はその数倍に達します。つまり、頭の中で読み上げる習慣を止めるだけで、読書スピードは2〜3倍に向上する可能性があるのです。
黙読の習慣を克服するための実践的トレーニング:
- 指やペンを使って視線を誘導し、強制的に速く読む
- 目で「意味のかたまり」を捉える訓練をする
- 最初は理解度が下がっても構わないので、とにかく速く目を動かす練習をする
初めは違和感がありますが、継続的な練習によって徐々に文字をダイレクトに意味として捉える能力が身につきます。
時間制限読書法:1冊にかける時間を制限して速読力を鍛える
読書は時間をかけようとすれば、いくらでも時間をかけられてしまいます。同じ箇所を繰り返し読んだり、理解するために前のページに戻ったりしていると、いつまでたっても1冊を読み終えることができません。
そこで効果的なのが時間制限読書法です。例えば「この本は2時間以内に読み終える」と決めてタイマーをセットします。制限時間があることで、自然と以下のような効率的な読書習慣が身につきます:
- すでに知っている内容や重要でない部分は読み飛ばす
- 本当に大切な情報に集中する
- 一度読んだ箇所に戻らず先に進む
最初は「全部読まないと気持ち悪い」と感じるかもしれませんが、練習を重ねるうちに必要な情報だけを効率よく取り入れる能力が向上します。これは、日々増え続ける情報に対応するために必要不可欠なスキルです。
内容理解と速読の両立:1回で全て理解するのは無理だと受け入れる
本を読む目的の一つは、書かれている内容をしっかり吸収することです。そのため、理解度を犠牲にして速く読むことに抵抗を感じる方も多いでしょう。
しかし現実的に考えると、どれだけ時間をかけて読んでも、一度の読書で本の内容を100%理解し記憶することは不可能です。脳科学研究によれば、人間の記憶は繰り返しによって強化されるため、1回の読書で全てを理解しようとするより、何度か接する方が効果的です。
この事実を受け入れることで、読書への心理的プレッシャーが軽減され、より自由に速く読めるようになります。おすすめの方法は:
- まず全体を2〜3時間で一気に読み通す
- 特に重要だと感じた箇所や理解が不十分な部分にマークをつける
- 後日、マークした部分だけを読み返す
この方法なら、1冊の本から得られる情報量を最大化しながら、読書時間を大幅に削減できます。
目的読書法:その本から何を得たいのか決めて効率よく読む
1冊の本から得られる価値は人それぞれです。数百ページある中で、あなたにとって真に役立つのはたった一つの章やアイデアかもしれません。もしその部分だけを知ることができれば、読書時間は大幅に短縮できるでしょう。
効率的な「目的読書法」のステップ:
- 本を手に取る前に「この本から何を得たいか」を明確にする
- 目次や索引を活用して、関連する部分を特定する
- 関連性の高い章から読み始め、必要に応じて他の部分へ広げる
本を読むきっかけは様々です。タイトルに惹かれたのか、著者に興味があるのか、誰かの推薦なのか。さらに、あなた自身が現在置かれている状況や課題によって、同じ本からでも得られる価値は変わります。
あなたの状況と本の内容を照らし合わせて「この本からこういう内容が得られたらいいな」と具体的に決めておくことで、余計な90%の内容に時間を割かずに済みます。
読書効率化の裏技:「ながら読書」で時間を有効活用する
どうしても読書スピードの向上が難しい場合は、発想を転換して「ながら読書」という選択肢も検討してみましょう。特に効果的なのがオーディオブックの活用です。
オーディオブックの最大の利点は、以下のような「ながら活動」と組み合わせられることです:
- 通勤・通学中のリスニング
- 家事をしながらの学習
- ウォーキングや軽い運動中の情報インプット
視覚的な図表が必要ない書籍であれば、耳で聴くことでも十分に内容を理解できます。「本を読む時間がない」という悩みを根本から解決できる方法といえるでしょう。
特に最新のオーディオブックアプリは再生速度の調整が可能で、慣れてくれば1.5〜2倍速での聴取も可能になります。これにより、通常の読書よりも短時間で1冊を終えられるケースもあります。
Amazonのオーディブルをはじめ、様々なサービスが30日間の無料体験を提供しているので、まずは試してみることをおすすめします。
読書スピードアップのための実践トレーニング
読書スピードを上げるには、具体的な練習が必要です。ただ早く読もうとするだけでは効果は限定的です。ここでは実践的なトレーニング方法を紹介します。
1週間で読書スピードを2倍にする練習プログラム
読書スピードを短期間で向上させるためには、計画的なトレーニングが効果的です。以下の7日間プログラムを毎日15-20分実践してみましょう。
1日目:基礎測定と目標設定 まずは現在の読書スピードを知ることから始めましょう。小説や一般書籍を5分間読み、読んだページ数×1ページの平均単語数÷5で、1分あたりの読語数(WPM:Words Per Minute)を計算します。一般的な日本人の平均は300-400WPM程度です。この数値の2倍を1週間後の目標に設定します。
2日目:指でガイドする練習 文章を読むとき、指やペンを使って文字を追いかける練習をします。これにより目の動きが効率化され、読書スピードが自然と上がります。10分間は普通の速さで、残り5分は少し速いペースで練習しましょう。
3日目:固定幅で読む練習 一度に複数の単語をひとまとめに認識する練習です。文章を読むとき、一行を3-4ブロックに分けて、一度に1ブロック分を認識するよう意識します。最初は理解度が下がりますが、続けるうちに慣れてきます。
4日目:リズム読書法 メトロノームや読書用タイマーアプリを使い、一定のリズムで読み進める練習です。最初は快適な速度から始め、徐々にリズムを速くしていきます。15分間、3段階の速度で練習してみましょう。
5日目:跳躍読書法 文頭と文末、そして重要そうな箇所だけを読む練習です。文章全体の構造を素早く把握するのが目的です。最初は理解度が下がりますが、文章の骨格を掴むトレーニングになります。
6日目:理解度確認と速度調整 5日目までの練習で速度は上がってきているはずです。この日は理解度と速度のバランスを取る練習をします。10分読んだ後、内容を要約してみて、どの程度理解できているか確認します。理解度が70%以上あれば適切なペースです。
7日目:最終測定 初日と同じ方法で読書速度を測定します。1週間の練習で、多くの人は30-50%のスピードアップが見られます。2倍まで到達しなくても焦る必要はありません。継続することで徐々に向上していきます。
この1週間のプログラムを終えた後も、毎日5-10分程度の練習を続けることで、読書スピードは維持・向上していきます。
スキミングとスキャニング:必要な情報だけを素早く見つける技術
読書のすべての場面で精読が必要なわけではありません。目的に応じて読み方を使い分けることが、効率的な読書の鍵です。
スキミングとは文章を斜め読みする技術です。本の内容の全体像を短時間で把握したいときに有効です。具体的な方法は以下の通りです:
- 目次、章のタイトル、小見出しを優先的に読む
- 各段落の最初と最後の文に注目する
- 太字やイタリック体などの強調された部分を重点的に読む
- 図表やグラフのキャプションに目を通す
スキミングは本を選ぶ際の下調べや、既読の本の内容を思い出すときに特に役立ちます。
一方、スキャニングは特定の情報を探し出すための技術です。例えば索引から必要なページを見つけ出したり、特定のキーワードが出てくる箇所を探したりするときに使います。
スキャニングのコツは以下の通りです:
- 探している情報(キーワードや数字など)を明確にしておく
- 目を縦方向に動かし、該当する単語や表現を見つける
- 見つけたら周辺の情報を確認して関連性を判断する
これらの技術を使いこなせるようになると、1冊の本から必要な情報だけを15-30分で抽出できるようになります。特にビジネス書や実用書では、すべてのページを同じ密度で読む必要はないため、スキミングとスキャニングのスキルが非常に有効です。
集中力を高めて理解度と速度を同時に上げる方法
読書スピードと理解度は、集中力の質に大きく左右されます。集中力が低下すると、同じ箇所を何度も読み直したり、内容が頭に入らなかったりして、結果的に読書効率が下がります。
集中力を高める環境整備:
- 通知をオフにしたスマートフォンは視界の外に置く
- 適切な照明と座り心地の良い椅子を用意する
- 読書専用の場所を決めて条件付け効果を生み出す
- 雑音が気になる場合は、ホワイトノイズや環境音楽を活用する
集中力を維持する読書テクニックとして、ポモドーロ・テクニックが効果的です。25分の集中読書と5分の休憩を交互に行う方法で、脳の疲労を防ぎながら効率良く読み進められます。
また、アクティブ・リーディングは理解度と速度を同時に向上させる強力な手法です。具体的には:
- 読む前に質問を立て、答えを探しながら読む
- 重要な箇所に付箋やマーカーで印をつける
- 余白にメモや疑問点を書き込む
- 各章の終わりで内容を自分の言葉で要約してみる
特に要約する習慣は非常に効果的です。読んだ内容を自分の言葉で簡潔にまとめることで、理解度が格段に上がります。デジタルツールを活用する場合は、メモアプリや読書管理アプリに要点をまとめるのも良いでしょう。
集中力と理解度を高めることで、脳が情報を処理する速度が向上し、結果として読書スピードも自然と上がっていきます。読書は単なる文字の認識ではなく、脳の情報処理能力を総動員する活動です。定期的なトレーニングによって、この能力全体を向上させることができるのです。
読書のタイプ別おすすめスピードアップ術
本のジャンルによって最適な読み方は異なります。ここでは、代表的な3つの書籍タイプ別に、効率的な読書法を紹介します。
ビジネス書を効率よく読むためのテクニック
ビジネス書は情報の即時活用が求められるジャンルです。時間をかけずに必要な知識を得ることが重要です。
ビジネス書を読む際は、まず目次と索引を活用して全体像を把握しましょう。多くのビジネス書は章ごとに独立した内容を持っているため、自分に必要な章だけを選んで読むことも有効です。
特に効果的なのが「SQ3R法」と呼ばれる読書技術です。Survey(概観)、Question(質問)、Read(読む)、Recite(暗唱)、Review(復習)の頭文字をとったもので、ビジネス書を効率的に読むために以下のように応用できます:
- 目次、まえがき、あとがきを読んで本の全体像を把握する(5分)
- 「この本から何を学びたいか」という質問を自分に投げかける(2分)
- 気になる章を選んで読む(章ごとに15〜20分)
- 重要なポイントを自分の言葉で要約する(3分)
- 学んだことをどう活用するか行動計画を立てる(5分)
このように1冊あたり30〜40分程度で読み終えることを目標にすると、多忙なビジネスパーソンでも読書量を増やせます。
また、ビジネス書の多くは結論が冒頭に書かれていることが多いため、各章の最初と最後を重点的に読むだけでも内容の8割は把握できるでしょう。
小説を早く読みながら楽しむ方法
小説は没入感や感情移入が重要なため、スピードだけを追求すると本来の楽しさを損なう可能性があります。しかし、適切な方法で読書速度を上げることで、より多くの作品に触れられるようになります。
小説を早く読むコツは、情景描写と会話文で読み方を変えることです。情景描写は全体的な印象を掴む程度でスピーディーに読み進め、会話文や重要な場面ではペースを落として丁寧に読むというメリハリが大切です。
視野を広げる練習も効果的です。普段よりも少し離れた距離から本を見て、一度に複数の行を視界に入れる習慣をつけましょう。これにより、自然と読書スピードが向上します。
読書の途中で内容を整理するため、章ごとに30秒程度の小休止を入れるのもおすすめです。「今までに何が起きたか」を簡単に振り返ることで理解が定着し、次の章もスムーズに読み進められます。
長編小説の場合は、2〜3日間に分けて読むことで集中力を維持できます。1回の読書時間は45分から1時間程度が理想的です。
専門書・学術書の効率的な読み方
専門書や学術書は高度な内容を含むため、理解しながら読むことが求められます。ただし、すべての内容を一度に完璧に理解しようとするのではなく、多段階読書法を取り入れると効率的です。
専門書を読む際の効果的なステップ:
- スキミング:全体を5〜10分でざっと見て、構成や主要概念を把握する
- ノートを取りながらの精読:重要な章を選んで、概念や用語の関連性を図式化しながら読む
- 反復読書:難解な部分は時間を空けて再読し、理解を深める
専門書は索引の活用が特に重要です。知りたい概念や用語から逆引きして、必要な箇所だけを集中的に読むことで時間を節約できます。
また、専門書を読む際はアクティブリーディングを心がけましょう。単に文字を追うのではなく、「この理論は〇〇にどう応用できるか」「著者の主張に対する反論は考えられるか」など、批判的思考を働かせながら読むことで理解が深まります。
理解が難しい専門書の場合、まず入門書や解説記事を読んでから取り組むことも一つの方法です。基礎知識を得てから本書に戻ることで、読解スピードと理解度が大幅に向上します。
最新の研究では、専門知識を習得する際は分散学習(同じ内容を時間を空けて複数回学ぶ)が効果的とされています。1回で完璧に理解しようとするより、複数回に分けて読み返す方が長期的な記憶定着に効果的です。
まとめ:本を読むのが遅いのは必ず改善できる
「本を読むのが遅い」という悩みは、適切な方法と継続的な実践によって 必ず改善できる問題 です。この記事で紹介した様々な方法を自分の状況や目的に合わせて取り入れることで、読書スピードを向上させながら積読を効果的に解消できるでしょう。
多くの読書愛好家やビジネスパーソンが読書スピードの向上によって大きな変化を実感しています。あるエンジニアは 音読をやめる技術 を習得することで、1ヶ月に読める本の数が2冊から8冊に増加し、キャリアアップにつながりました。また、育児中の方は 時間をしばる読書法 と オーディオブック を併用することで、年間100冊以上の読書量を達成しています。
自分に最適な読書法を見つけるには、まず現状の読書スピードを把握し、読書の目的を明確にすることが大切です。この記事で紹介した方法を一つずつ試して、自分に合うものを見つけ、少なくとも2週間は継続してみましょう。完璧を求めすぎず、少しずつ改善していく姿勢が長期的な成果につながります。
また、本の種類によって読み方を変えるのも効果的です。重要な専門書はじっくり読み、軽めのビジネス書は速読するというメリハリをつけましょう。読書の習慣化 と 適切な読書法の選択 によって、読書スピードが上がるだけでなく、知識の吸収量が増え、人生の可能性が広がります。
よくある質問と回答
- 速く読むと内容の理解度が下がりませんか?
-
適切なトレーニングを積めば、読書スピードと理解度を両立させることは可能です。むしろ集中力が高まり、理解度が向上するケースも多いです。ただし、最初のうちは理解度が少し下がることがあるため、練習後に重要なポイントを振り返る習慣をつけると良いでしょう。
- 何から始めるのが最も効果的ですか?
-
まずは頭の中での音読をやめる練習から始めるのがおすすめです。これは多くの人が無意識にしている習慣で、これを改善するだけで読書スピードが1.5〜2倍になることも珍しくありません。次に時間制限読書法を取り入れると効果的です。
- 電子書籍と紙の本、どちらが速く読めますか?
-
個人差はありますが、多くの人は慣れている方が速く読める傾向があります。電子書籍はフォントサイズの調整や検索機能が使えるメリットがある一方、紙の本は空間的な記憶が働きやすく全体像を把握しやすいという特徴があります。両方を状況に応じて使い分けるのが理想的です。
- オーディオブックで「読んだ」と言えますか?
-
読書の目的が知識やストーリーの獲得であれば、オーディオブックも立派な読書手段です。2025年現在、多くの研究でオーディオブックと目で読む読書の情報定着率に大きな差がないことが示されています。ただし、図表が多い本や参照が必要な専門書は視覚的に読む方が適しています。